クモハ52から優美な流線型気動車を捏造する07-下地塗りと再仕上げ ― 2025年06月14日 06:38
常磐線103系マト7補完計画01-着工、そして着工が伸びた理由 ― 2025年06月15日 06:00
新シリーズです。
10年以上前に作った、常磐線103系で最後まで残ったマト7編成。実車は10両編成ですが、この時は5両しか作っておりませんでした。ほぼ同時期に作ったマト31編成と組み合わせた10両編成で遊んでいました。
本当は客室窓がユニットサッシではない中間車がもう5両いるのですが、この5両が曲者で、ドアが全てHゴムの無い金属押さえ窓です。
しかしこと103系前期型に限って言えば、窓がはめ込み式ではないKATOのKOKUDEN以外は全てHゴムが窓ガラス側に表現されており、この技法が使えません。必然的にクハ103-274でやったようなサードパーティ製の金属押さえ扉に交換する工法となります。
あれから10年強。いつかは作りたいと思い、チマチマ車体キット(グリーンマックスのHQEキット)やら部品やらを調達してきたので、材料は揃っています。
しかし前回の工作でたった1両なのに手こずったドアの交換を5両・・・気が遠くなってきます。
ですが、これを乗り越えないと大迫力の103系15両編成は手に入りません。
という訳で103系中間車の工作開始。
まずは仙石線にしようと思い途中で放棄した中間車2両の塗装落としからです。
いつものようにIPAに漬け込み、塗膜が浮いたところで古歯ブラシで擦って塗装を落とします。
クモハ52から優美な流線型気動車を捏造する08-車体のディティーリング ― 2025年06月18日 02:47
車体表面の凹凸仕上げが終わったのでディティーリングです。
古い車両という想定なので、ウインドシル・ヘッダー・雨樋を取付。用いたのはPlastructの0.3mm角棒で、窓の上下端に流し込み接着剤で貼ります。
流電改の車体にシル・ヘッダーを貼ると、元の流電にシル・ヘッダーが無いこと、シル・ヘッダー自体のゴツさもあって、南満州鉄道のレールカー(ジテ)のような重厚な感じになりました。
引き続き、靴ずりと乗務員室手すりを取り付け。合わせて旧銀河モデルのパーツから半流線型用テールランプと100Wヘッドランプの金属パーツを取り付けます。
その後にベンチレータを取り付け。ほぼ同世代と勝手に想定しているキハ07を見習って、屋根両側にT字型の半ガーラントベンチレータを並べていきます。取付にあたって、一定間隔に垂直線を引いたマスキングテープを治具代わりにしました。
ベンチレータの接着が終わり、こんな感じに車体生地が完成。我ながら、渋い仕上がりになったように思います。
一方の湘南顔の岡山臨港改はというと、キハ17系と同世代(ちょっと先輩)の想定のため、ウインドシルのみ取り付け。車体だけ見てみると、あたかもキハ17系の一員にも見える仕上がりになりました。
次はいよいよ塗装です。
常磐線103系マト7補完計画02-試しに1両作ってみました ― 2025年06月21日 00:06
「案ずるよりも産むが易し」という訳で、重い腰を上げてドアの交換を開始。まずは試しにサハ1両のドア交換を進めます。
まずは車体に一体モールドされているドアを、カッターナイフで切り抜き、ヤスリで形を整えます。1箇所切り抜くのに10分近くかかりました。
金属押さえドアの比較。トレジャータウン製(左)とボナファイデ製(右)を比較すると、各部の解釈の他、上下寸法に大きな違いが見られます。
両方を切り抜いたドア部分に宛てがってみると、右のボナファイデ製の方が切り抜き部分により近い寸法になりました。トレジャータウン製のドアをHQキット103系に使うには、上下の削り込みが必要そうです。
片側4箇所のドアを切り抜くのに1時間近くをかけ、何とかサハ103の両側8箇所のドアが切り抜けました。
カッターの刃が滑って、複数の余計なところにつけた傷は、パテを塗って乾燥させます。
試しに説明書通りに爪を切った窓ガラスと床板(家に余っていたKATOサハ103のもの)とを嵌め込んで、出来映えのチェックです。
その後、くり抜いたドア部をヤスリで調整しながら、金属押さえドアを瞬間接着剤で貼っていきます。
あまり貼り付け位置が奥まらないように、かつ貼り付け面と車体表面とが極力水平になるように、気をつけて固定していきます。
下館レイル倶楽部運転会(2025年6月) ― 2025年06月22日 20:47
下館といえば・・・真岡鐵道のSL列車でしょう。
さて、定例会の会場について早速試運転。
改修前から脱線が多発していたクハ411-115のカプラー周りはやはり治り切っておらず、こちらの前面を使った連結は当面禁止としました。それ以外はちょっとしたメンテナンスをすればすこぶる快調に走ります。
一方こちらは、今年2月に購入してつい先日整備した常磐線415系の先祖、401系電車です。
以前作った403系非冷房車と併結して走らせましたが、こちらもすこぶる好調。かたやスプリングウォーム動力、かたやフライホイール付きM-13モーターと、動力ユニットの世代が全く異なりますが、きちんと協調しました。
走らせていて気がついたのですが、401系は全車車体マウントTNカプラー搭載ですので、TNカプラーを搭載した運転台と中間部を連結して、写真のような国鉄末期以降に見られた変則7両編成も再現できます。
空いた時間を使って、写真のように先頭のライト周りの整備も実施。古い製品なので、LEDではなく電球でライトを点灯させる仕組みとなっており、ライトの明るさが足りない模様です。
【お知らせ】
毎年好評の夏休みイベント「下館レイルフェスタ」ですが、今年は7月20日(日)に開催する予定です。
写真は去年の開催状況です。(上がHOゲージ、下がプラレール。このほかにNゲージの展示運転あり)
詳細が分かりましたらここでも追加でお知らせします。
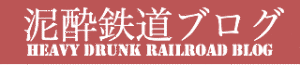


























最近のコメント