急遽の新パソコン導入 ― 2024年07月27日 07:41
パソコンが壊れたので、出費は痛いのですが急遽新パソコンを導入しました。
長年Macを使っているので、購入したのは今回もMac。で、ノート型で一番値段の安かった「MacBook Air M2」を注文、3日ほどで着荷しました。
2022年製造開始モデルということで若干の古さは否めませんが、それほどパソコンで高度な作業をする訳ではなくスペックに拘りはないのと、何より円安のご時世「安さ」に背に腹は代えられません。
早速開封してセットアップ開始。今まで頑張ってきた旧MacBook Air(2014年モデル)と並べてみます。
ちょっと本体寸法が小さくなった感じで、モニターの縁が小さくなり画面が大きく見えるようになりました。
厚さは・・・だいぶ厚くなりました。
旧MacBookが、手前に向けて薄くなる楔状の形をしておりシャープな手触りを実現していたのですが、それが廃止になり従来の平凡な断面形状に戻っております。
旧パソコンは電源は入るものの電源からの給電ができなくなり、バッテリー容量もおぼつかないため旧パソコンからのデータ移行は諦め、取ってあったバックアップからデータを移行します。
そんなこんなで一晩ほどでセットアップが完了。
使ってみた感じは・・・確かにYouTubeとかの画面展開が早くなった気がします。あと画面が綺麗です。
あれと思ったのが、モニター上面にカメラ用を避けるために欠き取りがありモニター画面が凹状になっているのですが、これはメニューバーに干渉することから、今のところあまり気になりません。
また10年くらい長い付き合いになることを願っています。
車両のメンテナンス ― 2024年07月24日 06:27
富山タイプ特急電車の工作10-上塗り2色目・3色目 ― 2024年07月21日 09:46
早起きして、10日ぶりに富山風自由型特急の工作を続けます。朝の暑くならない時間帯に塗装できるよう、マスキングを進めます。
塗り分けは、時代背景的(富山地鉄が標準色を変更した1990年代〜2000年代初頭に新造された設定)には黄色と緑のツートンの方が適切かもしれませんが、富山地鉄といえばこの色!のベージュ・グレーに赤帯にしました。
暑くならないうちに塗装。
マスキングした箇所に車体色のベージュを再度吹いて滲み防止、乾燥したらグレー(GM#35)を車体と屋根に吹きます。
さらに窓周り以外をマスキングして、窓周りのブラックアウトの表現。艶消しブラック(クレオス#33)を吹き付け、窓周りの表現の差を目立たなくします。
塗り分けの乱れもなく、見るだけで登山地鉄感がします。
ブラックの面積が大きく成田エクスプレスみたいで、ちょっとグレーの面積が少なかったかもしれません。
快楽園27-はじめてのレイアウト電照 ― 2024年07月20日 09:20
久々の快楽園の工作です。
日本帝國鐵道さんと話している中で「電飾はいいぞ」となり、快楽園モジュールもはじめて電飾することにしました。試しにジオコレの電飾キットを購入。
配線をクネクネさせながら、どう電照してやろうか構想を練ります。
ちなみに電飾LEDのうち1個はクリアーオレンジに塗装しました。
もそもそと工作開始。まずはレイアウトモジュールに6ヶ所孔を開けます。
孔をカッターナイフで削り広げ、電照用のLEDを上から通して配線します。
配線が終わったところでテストでスイッチポン。。。
電照の結果は写真の通り、大変フォトジェニックです。
なお電池ユニットはレイアウトモジュール台枠内に納まらなかったため、レイアウト背面の発泡スチロールを無理やり削って収めました。
新・中古カメラ導入〜オリンパスTG-6 ― 2024年07月17日 18:10
泥酔鉄道ブログを支えるデジカメは、いろいろ紆余曲折がありましたが、ここ数年は水陸両用で使えるオリンパスTG-870を使っています。
タフで不便はないカメラなのですが、模型工作撮影用には必ずしも使い易いとは限らないところもあり、どうしたものか思案しながら惰性で使ってきました。
前に個展で会って話したボシさんの写真集がオリンパスTG-6で撮られていたことを思い出し、ヤフオクをつらつら見ていたら動作未確認の使用感マシマシ個体が相応の値段で転がっているのをハケーン。
そんな訳で「模型工作撮り専用カメラがあってもいいじゃない」と思い清舞しました。
深紅のボディ、使い込まれた躯体はジャンク感すら漂いますが、フィールドカメラのタフな勲章と思えば全く目障りに感じません。
動作未確認で使用感ある個体ということで動くかどうかギャンブルでしたが、幸いにも各機能しっかり動作したので一安心。
早速、鉄道模型ファンがオリンパスTG-6を推す「深度合成」機能を試してみました。
こ う か は ば つ ぐ ん だ !
被写体に近づいて撮るマクロ撮影では、ピントが合った狭い範囲以外はボケてしまうものの、ピント合わせを複数箇所で行った複数の写真を合成して1枚の写真にする深度合成機能。上の写真にあるように合成後はボケが少ない、遠くから撮った実物のような写真が高いレタッチソフトを使わずともカメラの機能で手に入ります。
あと見逃せないのがカメラのレンズ位置が低いことから、無理してカメラを逆さにしなくても低いアングルからの写真が撮れること。TG-870では工夫を強いられていたところでもあるので、何気に助かります。
そんな訳で携帯カメラも合わせて三刀流になった泥酔鉄道ブログのカメラのお話でした。。。
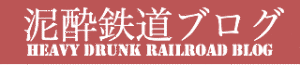



















最近のコメント