2025年「お雛様の森を電車が走る」(真壁のひなまつり) ― 2025年02月09日 05:32
展示はこんな感じで、ひな人形が並ぶ中をHOゲージとNゲージとが走る展示です。
場所は桜川市真壁町の旧市街地、旧田崎人形店(マップ番号C-41)です。
3月3日まで開催です。東京都心からはちょっと遠いですが、お近くにお立ち寄りの際はぜひ足を運んでみてください。
トミックス401系 ― 2025年02月11日 19:46
製品化発表から10ヶ月の時を経て発売されました、トミックス国鉄常磐線401系(高運転台・新塗装)のNゲージ模型を購入してきました。
早速余談ですが、今月は旅行やら車の車検整備やらで金欠気味でしたので、今まで貯めてきた量販店のポイントを、ここぞとばかり全投入し、30年前の415系4両編成相当の値段で何とか調達できました。
さて、早速開封・・・うーん、素晴らしい
各所の作り込みは、30年前の模型よりさらに考証正しくなされ、ディティールもふんだんでかつ破綻の無い仕上がりになっております。さすが定価2万円超orz。
特に出色なのは、ちゃんと403系・415系とは作り分けられたモハ400の屋上機器。交流20000ボルト・直流1500ボルトの双方の電気を取り入れて走ることのできる401系のキモというべきディティールがちゃんと表現されています。
床下や車体も、ちゃんと交直両用電車用に作り分けられており、今までの流用品とは異なりちゃんと事故なく交流区間に入れるようになっています。
さてこの模型は、1960年代前半の高運転台になりたての時期(屋上の雨樋の位置などが異なっております)の車両を模型化したものですが、その作り込みを旧作(α-モデルキット改造)クハ401と見比べてみましょう。
まず目を引くのはヘッドライト。レンズの裏のモールドまで表現されております。そして車体色。キット組立の403系はちょっとベージュが青味がかっている気がします。ベージュは難しい。。。
そして側面の比較。クハ401はクハ111/115に比べて若干長く、トミックスのクハ401はこれを再現しております、α-モデルのキットは何故か車体長が若干長くクハ401と同じ長さになっております。
で、同じトミックスのクハ411旧製品と比べてみれば・・・
クハ411の方が若干車体長さが短い結果となりました。
別パーツの取り付けやインレタの転写など、細かいディティール工作が残っておりますが、これらはじわじわ楽しむとして、とりあえず中敷のインレタを別売の12両入るタイプに交換し、多くの車両が収納できるようにしました。
快楽園48-バックパネルの設置 ― 2025年02月12日 20:25
レイアウトモジュールの背面。発泡スチロールに木目調シートを貼るだけではヨレヨレで興醒めなので、 シャキッとした背面を目指すべくモジュールにバックパネルを設置します。
以下に述べる手直しの経緯から、バックパネルの設置は、本当は最初にやっておくべき工程でした。
バックパネルに使ったのは1mm厚のバルサ板。ホームセンターで買うことができます。
前回の工作で貼った木目調シートを剥がし、バルサ板に発泡スチロール用接着剤を塗ります。
発泡スチロールとバルサ板の双方に塗った接着剤が乾燥したら、両者を圧着して止めます。
接着剤を完全に乾燥させた後、接着したバルサ材をカッターで元の地形に合わせて切っていきます。薄いバルサ材なので、困難なく切断できます。
その後、元の地形とバックパネルのバルサ材との間に出来た隙間を粘土で埋めます。
この隙間埋めの工程、バックパネルのを取付を最初にやっておけば、地形づくりの工程と一体で進められ、不要になります。
隙間埋め部分の粘土が乾いてから、表面の草や砂利敷きをパウダーで元と同じように再現します。
パウダーが乾燥したら、再度バックパネルに新たに切り出した木目調シートを貼ります。
まだちょっとシワが寄っているような気がしますが、垂直がしっかり出るようになりました。
EH500型電気機関車を購入しました ― 2025年02月15日 21:53
毎日通勤途上で見る、貨物列車を牽くEH500型電気機関車。地元の車両なのでかねがね欲しいなと思いつつも、動輪が8個付いているせいか新品・中古ともなかなか高嶺の花状です。
しかし某日某オークションを見ていたら、未使用品と思われるトミックスの2010年ロットの機関車が手が届く価格で流れてきましたので、思わずポチ。
今月・来月と色々モノイリなので、今まで貯めてきたオークションの売上金を全投入するとともに、残った差額はしばらく先の4月の家計簿から差し引くことにしました。駄目ですね。。。
ポチして数日後、商品が無事に届いたのを確認して、転入整備。
まずはナンバープレートやアンテナ・断流機の別付パーツを取り付けます。ナンバーは特に由来はありませんが18号機にしました。
次に片側の連結器を製品付属のTNカプラーに交換し、見栄えの向上を図ります。
その後屋上機器の塗装。碍子をフラットホワイト、パンタグラフスリ板・屋上配線をダークコッパーのエナメル系塗料で塗ってあげます。
かくして整備完了です。
で、今日夜の下館レイル倶楽部でコンテナ車19両を引き連れて試運転。低速も効いて快調に走りました。
415系電車の修繕07-クハ411の車体長延長 ― 2025年02月16日 09:19
クハ401と比べ僅かに(スケール換算で1mm強)車体長が短いことが発覚したクハ411。差は僅かなので迷いましたが、おかしくならない範囲で車体長を直すことにしました。
まず運転台と客室の間をカッターナイフで切り離します。
レザーソーは切断幅が大き過ぎてディティールに影響が出るので使いません。
運転台と客室とが切断できたら、切断面に0.5mmプラ板を噛ませて接着します。スケール通りの1.5mmの車体延長は、切り継ぎによる車体の「伸び」を考えるとやり過ぎのような気がします。
切り継いで車体長を伸ばした箇所に、パテ盛りで隙間を埋めて、乾いたら表面を削って仕上げます。
こんな感じで車体長の延長完了。加工前(下)と比べてみますと、ほんのり車体長は長くなりました。仕上げ漏れがあるかどうかは後日サーフェーサーを吹いてチェックします。
この加工ですが、接着剤・パテが乾燥するのを待つ関係で1週間を要しました。もう1両のクハ411も今後同様の加工を行います。
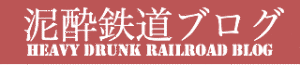






























最近のコメント