快楽園に似合うクルマ ― 2025年04月03日 01:23
快楽園に似合うバスとのことで、1960〜80年代の関東鉄道バスを捏造しているところです。
春の衣替えに合わせて押し入れの奥からカーコレクション(安い時に見境なくいっぱい買っておいた奴)を出して、快楽園に似合うクルマを捜すべく、こちらも棚卸ししていました。
その中で、バスと時代考証が合う、1960〜80年代の自動車を見繕いました。
1960年代代表は、ポルシェとのデッドヒートで「伝説」を打ち立てたS54スカイラインGTとトヨタあたりの小型ボンネットトラック。1970年代代表は、黄色い日通トラックと懐かしいKATOのクラウンセダン。1980年代代表はゴールドのマークⅡとセリカXX。このあたりを快楽園モジュール専属自動車に仕立てることにします。
あと、もう少し快楽園に人口を増やしたいなと思っていたところ、未使用ストックの人形が出てきましたので、こちらも追加配置します。
グリーンマックス創業50周年記念誌 ― 2025年04月02日 06:51
今年で創業50周年になる鉄道模型メーカーのグリーンマックス。当方でもかなりいろいろ同社製キットを組み立ててきましたが、この度50周年記念誌が出版されました。
税抜8500円と、この手の書籍としてはかなり高額だったこともあり、だいぶ逡巡しましたが、「買わない後悔よりも買う後悔」との思いで購入しました。
早速、待ちきれずに電車の中で開封。取り急ぎ長年パッケージや説明書のイラストを描いてきた小林信夫の章を先行して堪能。パッケージ画集いっぱいで、それだけでも大満足です。
その後、高級なウィスキーを嗜むようにチビチビと読み進めていますが、同社の創業当時のエピソードや未発売品の裏話などもふんだんに盛り込まれており、やはり買ってよかったとの思いでいっぱいです。
著作権の関係でイラスト転載は自重しますが、ネットミームにもなった「何らかの方法で埋める」「この部分自作した方が早い」のイラストも再録されており、思わずニヤリとしました。
税抜8500円と、この手の書籍としてはかなり高額だったこともあり、だいぶ逡巡しましたが、「買わない後悔よりも買う後悔」との思いで購入しました。
早速、待ちきれずに電車の中で開封。取り急ぎ長年パッケージや説明書のイラストを描いてきた小林信夫の章を先行して堪能。パッケージ画集いっぱいで、それだけでも大満足です。
その後、高級なウィスキーを嗜むようにチビチビと読み進めていますが、同社の創業当時のエピソードや未発売品の裏話などもふんだんに盛り込まれており、やはり買ってよかったとの思いでいっぱいです。
著作権の関係でイラスト転載は自重しますが、ネットミームにもなった「何らかの方法で埋める」「この部分自作した方が早い」のイラストも再録されており、思わずニヤリとしました。
【誰得企画】首都高速東京駅降り口を探検する ― 2025年03月30日 23:41
1ヶ月前に来月5日で廃止になる東京高速道路をさよなら運転した際、X(Twitter)かグループラインかで「東京駅降り口は行かないの?」とのコメントをいただきました。
東京駅降り口とは、首都高速道路八重洲線の八重洲インターチェンジに隣接する、東京駅八重洲地下街に直結する降車専用の車寄せで、ここを使うと首都高速を降りることなく東京駅に向かう人を降ろすことができる、という知る人ぞ知る(タクシー運転手でも知らない人がいるくらい)迷スポットです。八重洲線の南行・北行の両方に降り口が用意されております。
なお、この降り口は読んで字の如く降車専用で、ここで待ち合わせたり人を乗せたりすることはできません。
この八重洲降り口ですが、来月5日の八重洲線長期通行止め(首都高速リニューアルの都合で10年近く通行止めになる)で、しばらく使えなくなることが決まっていますので、今更ながら(本当誰得ですね)使ってみての紹介をしたいと思います。
まずは運転手の確保。神奈川の実家に帰る妻に頼み込んで(なんでも首都高都心環状線は怖くて運転したくないらしい)、何とか承諾を得て首都高八重洲線へ向かいます。検討の結果、妻の運転が比較的楽な南行降り口に突撃することにしました。
写真の神田橋ジャンクションから首都高八重洲線が分岐しますが、来たる4月5日の八重洲線通行止めに合わせてジャンクションが廃止?移転?されることから、一部標識が撤去されています。
そのまま八重洲トンネルに入り、八重洲インターチェンジで降りる直前で「乗客降り口」の方に曲がります。
そして・・・
首都高速八重洲乗客降り口(南行)に到着。
照明が必要最小限しか点いていないことから構内は薄暗く、本当にここで降りて東京駅に直結しているのか?と思われる雰囲気の場所でした。
ここで車を降り、妻運転の車がそのまま神奈川方面に向かうのを見送ります。
なお、10分近く降り口周辺に止まっていましたが、誰も降り口は利用しませんでした。
タイル張りの暗い構内の両端に、歩行者出口の扉があります。
一応扉は水色に塗られており「ヤエチカ・東京駅方面出口」「一旦出たら戻れません」とペイントで書かれております。これでもまだマシな方で、同じ八重洲乗客降り口でも北行の方は「ヤエチカ・東京駅方面出口」「戻れません」とシールが貼ってあるだけで、より殺風景らしいです(ネットで見れます)。
扉を開くと、急な登り階段が待ち構えています。
階段を出て、扉を閉めてから出口の扉を開こうとしましたが、ドアノブが固定されておりドアが開きません。
確かにこの降り口には鍵を持っている人以外誰も入れない(出るだけ)の構造です。
ネットやYouTubeで見た記事は北行降り口のレポートが多く、予習した限りでは、急な階段を登れば煌びやかな八重洲地下街に直結している先入観を持っていました。しかし南行降り口は、この階段を登っても殺風景なオフィスや貸会議場(日曜日なので閉まっている)があるだけ。当然人はほとんど歩いていません。
曲がりくねった通路を100mほど歩いて、ようやく営業中の床屋を見つけましたが、そこで行き止まり。
どうしたものかと辺りを見回しましたが、地下1階に繋がる登り階段があり、その階段を登ってようやく八重洲地下街のメインストリートに出ることができました。ちなみに地下2階に「理容マツナガ」さんの店舗がある場所に出ます。
いや〜何から何まで怪しかった。。。正直、これが東京駅につながっているのか、だいぶ不安になりました。
あと6日で使用休止になることから誰かの役に立つとは思えない八重洲降り口探検記でしたが、東京駅に眠る迷スポットとして、行ってよかったと思いました。
快楽園の関鉄バス04-後部点検蓋・ルーバーまわりの工作 ― 2025年03月29日 05:53
関東鉄道バスでは、ボンネットとかキャブオーバーの時代は別にして、UD(日産ディーゼル)車は西武中古が入るまでは居なかったので、工作中のバス2台も関鉄バスで多数派だったいすゞ車に化けてもらいます。
UDといすゞとで位置が異なるバックランプ・ナンバープレートを一旦切除します。
ルーバーや点検蓋も不要なものはパテ盛りで塞ぎます。
合わせて、写真一番左の、元琉球バス交通のトップドア車(フリー塗装のバスに化かすつもりです)は、ライト周りの日野車っぽい造形に敬意を表して、こちらもモデルのUD車から日野車に見えるようリア周りを改造。
一旦ウインカーを削り、日野車っぽく見えるようルーバー上部と点検蓋上部とを埋め、ルーバーと点検蓋が平滑になるように削ります。
爪楊枝の先に400番の紙ヤスリ片を接着した簡易工具で削りますが、平滑になるまで削るのが結構だるいです。。。
べ、別にUD車が嫌いな訳ではなくて?
2サイクルUDエンジンの重厚かつ軽快な吹け上がりとか最高じゃないですか??(いつの時代の話だ???)
リアを平滑に削り終わったら、点検蓋のモールドの再現です。
いすゞBA・BU、日野REの点検蓋の開き方を勉強し、見よう見まねでカッターナイフで点検蓋の形状に切り込みを入れていきます。
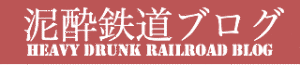




















最近のコメント