鬼怒電'25標準車1000-01_設定とベース車体について ― 2025年10月29日 03:27
変な時間に起きてしまったので、変な時間に更新です。。。
「鬼怒電」と称して、茨城・栃木を走る架空の電鉄をイメージして、自由形車両の工作を継続的に続けています。
鬼怒電の電車を語るにあたり、「標準的な車両」がいる方が何かと妄想が捗るのではないかと思います。標準あっての異端、ということで。。。
「標準的な車両」のストーリーはこんな感じです。
「1970年代に、沿線の宅地開発が進んだことで近代的な電車が必要となり、木造車・釣掛駆動車・譲受車ばかりだった鬼怒電に新機軸を導入した20m級3扉の新造車が多数(3両編成3本、2両編成5本)導入された。これらの新造車は期待を込めて新しい付番規則の「1000系」が付けられた。以来、冷房化・運転台増設・ワンマン改造を経て半世紀以上鬼怒電で重用されてきたが、2025年現在老朽化が進みその取り替えに鬼怒電首脳陣が頭を悩ませている」
模型での改造ベースはグリーンマックスの国鉄101/103系。20m級4扉のこの電車を、切継工作で20m級3扉にします。窓配置は101/103系の窓配置の中間を置き換えた、扉間窓4つとします。文章だけでは分かりにくいと思いますので、旧作の写真を見て頂いた方が早いと思います。
実物の電車ではもう少し両端の扉が中央に寄った扉間窓は3つのケースが多いです(両開き3扉で客室窓が4つの事例は、だいぶ時代が下ったJR東日本701系が初めてだったと思います)。敢えて車内流動で不利な扉間窓4つとした理由として、1000型の製造が始まった1970年代当初、鉄道でも採用が始まったばかりの「ワンマン運転」を想定してのためと言われています。結果的にそれが功を奏し、当時の鬼怒電首脳陣の先見性が優れていたことを物語っています。
で、模型。この旧作の車体更新・整備に合わせて、標準車らしく長編成(とは言っても地方私鉄なので3両程度ですが)を組めるように新規で車両を拵えようと思います。ベース車両は丁度良い具合に、京葉線103系の車体更新で余った103系電車の車体6両分がいます。
これは2001年頃に、グリーンマックス101系キットから組んだもので、103系エボリューションキットに車体を更新した際に余ったものを、廃棄せずストックしておいたものです。某氏に負けず劣らず、自分も結構な貧乏性です。。。
これの車体を分解・切継・再組立して、鬼怒電1000系に仕立てることにします。
鬼怒電ものがたり'24-万博車とサステナ車両11(完成) ― 2024年12月29日 00:17
鬼怒電の「万博車」と「サステナ車両」とが完成しました。
11両がケースに入ると、なかなか壮観です。
最後の仕上げ、私鉄っぽいL字型の無線アンテナを取り付けます。
使ったのは我が家に在庫のあるトミックスの古いレッドアロー用無線アンテナ(JA02)。古い製品ながら適切なモールドと強度のため愛用しております。
かくして現代の鬼怒電を走る2編成が完成。
こちらが万博車。1980年代半ば以降の新造車のデザインを先取りした意欲作です。
一方こちらがサステナ車両。東急9000系の短編成化で余った中間車を再用した車両で、鬼怒電初のステンレス車にしてVVVF制御車です。
最後に小さいスカートを増設し、前面のアクセントにしました。
【鬼怒電ものがたり'24-万博車とサステナ車両 まとめ(2024.11-12)】
鬼怒電ものがたり'24-万博車とサステナ車両10(前面窓ガラスと方向幕) ― 2024年12月28日 05:42
東急9000系改造の鬼怒電サステナ電車。前面窓は最初はめ込み式ではなく裏貼り方式にしようとしていましたが、やはり見てくれで未練が残りそうでしたので、はめ込み式で作ることにしました。
そんな訳で、窓ガラスを窓の寸法に切り出してはめ込みます。今回窓ガラスに使ったのはエンドウのキャブロイド板。柔らかくて加工しやすいです。
しばらく乾燥。前面窓のボンドが固まりました。
ボンドの塗布量が少々多かったかもしれません。。。あとキャブロイド板の切断面が白く目立ってしまっています。
(この後、キャブロイド板の切断面を黒く塗り、前面窓ははめ込み直しました)
鉄道コレクション改造の万博車の方は、Nゲージ鉄道模型としてちゃんと走るよう、ウェイトを積みます。
ウェイトはコスト縮減の観点から、別売りの鉄コレ走行ユニットのウェイトでなく自宅に余っていたGMの棒ウェイトを使用。これを黒く塗り、室内に接着剤で止めます。
室内ディティールは損なわれますが、コスト縮減には代えられません。
仕上げに、前面に方向幕を入れます。
東急9000中古の方は、オレンジ色のテプラから作った「茂木」のLED幕を貼ります(先日のバスコレと同じ技法です)。
一方、万博車の方は鉄コレ常総線ステッカーの「下館」を切って貼りました。
前面ガラスの後ろに表示される方向幕がいい感じです。
鬼怒電ものがたり'24-万博車とサステナ車両09(インレタとクリアー吹き) ― 2024年12月25日 06:21
車番をインレタで転写します。インレタは自宅で余っていたトミックス211系のインレタを流用。古いインレタですが割とちゃんと転写できました。
鬼怒電の車番は「0〜999:旧性能車」「1000〜1999:新性能車」「2000〜2999:譲受車」という規則でつけられているという想定をしています。
であればVVVF制御の新系列車は「3000番台」だろう、ということで、JR211系のインレタを使い「3001-3501」のナンバーを付けました。
一方万博車のナンバーは、先の命名規則に従って1000番台、その中でもマイナーチェンジをした1500番台(1501-1601)としました。(サポって前面ナンバーは省略・・・)
合わせて、靴ずりにシルバーのインレタを貼ります。
合わせて、ナンバーの転写が終わったら、車体にインレタ保護のクリアーを吹きます。
クリアーが乾いたら、屋上機器(クーラー、ヒューズ、避雷器)を接着します。
このペースなら、年内には完成できそうです。
鬼怒電ものがたり'24-万博車とサステナ車両08(車体・屋根・床下の塗装) ― 2024年12月22日 00:06
週末を待ちきれず、平日の夜からチマチマと少しずつ車体塗装を始めました。まずは帯色のオレンジ(朱色4号)から。
・
・
・
( ゚д゚) ・・・ (つд⊂)ゴシゴシ (;゚д゚) ・・・
・
・
・
どう見ても伊予鉄です。本当にありがとうございました。
帯の塗装が終わったところで車体の塗装です。
まずはサステナ車。帯をマスキングして、車体色のシルバーを普通に吹きました。塗り分けは元の東急9000を踏襲します。前面も塗装します。
マスキングを剥がしてみると・・・
なるへそ。帯がオレンジだった世界線の伊豆急にも見えてきて、悪くない感じです。
万博車もマスキングをして塗り分けを実施。万博車は「鬼怒電新性能電車」共通の、車体はクリーム色4号に裾はダークグレー(GM#35)の塗り分け。前面の帯部分は元の121系のモールドを活かした塗り分けにしました。こちらも、前面窓周りを艶消しブラックに塗って引き締めます。
イキオイで、床板・床下機器、台車、クーラー等を塗装します。床下・台車は万博車は軍艦色(2)でサステナ車は元の東急9000に準じた艶消しブラック。クーラーはライトグレーと銀色に塗装します。
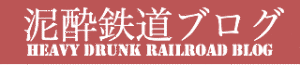






















最近のコメント