「ナナサンマル」 ― 2015年07月09日 23:30
昨日、酒席を一緒していただいた方が沖縄出身で、しかも携わる仕事の絡みか
「ナナサンマル」の意味を理解して強い反応を頂き、沖縄行目前に想定外の燃料を注がれました。
前回のブログ記事で「ナナサンマル」車の話を少し書きましたが、今回の更新では、ナナサンマルから17年経った2000年当時、ごくごく普通に活躍していた彼らを紹介します。
ますは那覇市内線を受け持つ那覇交通。2004年に那覇バスに会社が変わっています。
車両はナナサンマルの際いすゞに統一され、デコトラのようなバンパーを付けて那覇市内・近郊を運行していました。
写真 の1518号車は、近年の塗装塗り替えられた1台ですが、じつはこの車両こそが、沖縄本島の交通が一斉に左側通行に変わった1978年7月30日、那覇市内線の初便として左側通行に変わった那覇市内にはじめて繰り出した車両です。
この写真を撮った2000年当時、経営面では非常に厳しい環境に置かれていましたが、車両は再塗装され錆も無い姿で活躍していました。
バス趣味なるものが全っったく認知されておらず、交差点角の交番からでてきた「おさわりまん」にいろいろ訊かれたのも、いい思い出です。
次は沖縄本島に路線網を持つ琉球バス。こちらも2005年に琉球バス交通に会社が変わっています。青とオレンジで波を表現したかのような塗装が印象的です。
車両はナナサンマルの際に、日産ディーゼルと日野に統一。以前は島内の米軍スクールバスも受託しており、青とオレンジが入れ替わった塗装の車両も多数いました。
写真の車両は朝限定の急行バスで、太平洋側の具志川から文字通り本島を横断して那覇に着いたばかりの車両です。スコールのような通り雨を吸った路面に、「急行」サボも誇らしい車体が反射していました。
こちらは沖縄バス。ここだけは経営破綻せず戦後からの会社が存続しております。また、「ナナサンマル」車の取り替えも他社より進んでいるように見えました。
こちらは三菱ふそうに統一され、屋根後ろが丸い、1978年当時でも古めかしい当時でも古めかしいG4車体を持つ車両が導入されました。
後に1064号車が動態保存され、さらにバスコレで模型化もされ、全国的に有名になったモデルです。
最後は東陽バス。観光スポットの少ない沖縄東部を担当しています。車両は日野を選択、後年の車両更新で大型方向幕に改造された車両も多数いました。沖縄の車両板金・改造技術の高さを物語っています。
こちらも「ナナサンマル」車の1台(906号車)が動態保存されており、定期的に営業運行しております。
沖縄旅行2015-1 飛行機に乗るまでが旅行 ― 2015年07月11日 14:30
今年も、ありがたい事に年に一度の夏の旅行シーズンがやってきました。
今年は世の中が夏休みに入る前のオフシーズンに夏休みを取れ、土日を入れて5連休になりました。
栄えある初日、夜明けと共に始まる旅のスタートは。
いつもの宇都宮線始発、いつもの520M(いまは1521E、っていうんでしたっけ?)です。仕事が終わらなくて完徹してました(爆)
去年もこんな感じだったような。。。
で、行き先は沖縄。関東地方からですと羽田から飛行機に乗っていく必要があります。
一旦帰宅して家事をしてから、満を持して上野東京ライン、品川乗り換えのコースで出発。しかし。。。
10両編成の電車の車内は混雑、自分たちは大きなキャリーバッグを抱えていることもあり、ものすごく気兼ねしてしまいます。
そのため。。。
赤羽で上野東京ラインを放棄し、京浜東北線に乗り換えて浜松町乗り換えのコースに変更しました。
赤羽から浜松町まで、快速でも27分かかります。上野東京ライン開通の影響もあり、思ったより時間がかかっています。
浜松町で東京モノレールに乗り換え。休日の11時ごろの便だというのに、割と空いていました。かぶりつき席をゲットできたのは良いのですが、品川に止まり浜松町を通過する上野東京ライン開業の影響を受けているようで心配になってきますが、東京モノレールと京浜急行の混み具合は、今年の春からどうなったのでしょうか。
大荷物を持って移動、ということもあると、荷物の持ち歩きやすさも心配されてもよいような気がします。
しかしモノレールの列車写真ってなかなか取りにくいです。
そんなこんなでやっと羽田到着。
飛行機を待っていると、日本国内では久しく見なくなったジャンボジェットを発見。しかも政府専用機でした。
はてさて、どんな旅行になるのでしょうか。
沖縄旅行2015-2 戦後70年、「ケービン」の痕跡を追う ― 2015年07月13日 06:00
沖縄に着いた翌日は、妻の運転練習も兼ねて、バスではなかなか行きにくい、本島東部の海中道路方面を観光しましたが、その帰りに1箇所立ち寄りたいところがありリクエストをして寄ってもらいました。
少し古めかしいコンクリート造りの平屋建に、途中で切れた9本のコンクリート柱。
実はここが、戦前に沖縄島内を運行していた「沖縄県営鉄道」の終点、与那原駅舎です。
ここから、写真奥手の那覇方向に、鉄道路線が走っていました。
沖縄県営鉄道は、1914年に那覇から東海岸の与那原町まで開業し、以降南部の糸満市・中部の嘉手納町まで開業した鉄道です。
規格は、黒部のトロッコ列車なみの線路幅76cmと、線路幅が1m以上ある通常の鉄道と比べて小ぶりな「軽便鉄道」と呼ばれるもの。それが鈍って、「ケービン(軽便の訛り)」とも呼ばれていました。
いまでこそ沖縄本島各地は道路が網の目のように整備され、自動車で難なく物流を行うことができますが、戦前当時は道路も自動車も全く発達しておらず、那覇から本島北部への輸送はもっぱら船に頼っており、船の発着点として与那原町は大きく発展していました。
那覇・首里と東部の連絡拠点であった与那原を結ぶため、県営鉄道は最初に与那原まで作られたものと思われます。
鉄筋コンクリート製の駅舎から振り返ると、港までまっすぐ伸びる通りが駅を行き止まりにして伸びています。
全国各地の多くの鉄道駅がそうであったように、駅の建物を起点にしてまっすぐ伸びるこの通りは、まぎれもなくここが鉄道駅であったことを強く物語っています。
駅舎は、軽便鉄道にしては珍しいコンクリート製のものでしたが、ちょうど70年前の沖縄戦で破壊され、軽便鉄道自体もそのまま運行を終え、鉄道用地は道路や軍用地に、線路は軍用の鉄材に転用されて行きました。
与那原駅舎自体は(コンクリート製でしたので)骨組み等が残っており、これを再利用して与那原町役場庁舎に再築され、役場や農協の施設として使われていました。
現在、与那原駅舎は、与那原町で「軽便与那原駅舎展示資料館」として、軽便鉄道当時のコンクリート平屋建ての建物に建て直されています。
「途中で切れた9本のコンクリート柱」は、役場として使用されていた初代与那原駅舎の部材で、これだけは当時のものが残っていました。
展示館内は軽便鉄道当時の資料や備品類・再現ジオラマ、映像資料が展示されております。
展示館の入場券は当時の切符風、日付は本物の打刻機に自分で通して入れられます。
沖縄戦後の混乱で、なかなか当時の遺構が残っていなかったり文字通り地中に埋まっている沖縄県営鉄道の痕跡ですが、遺構も資料館として整理展示する枠組みができたこともあり、大事な資料としてずっと残していきたいものです。
一方の軽便鉄道の発着点である那覇、こちらはバスターミナルとして使用されています。
現在は・・・
バスターミナル自身が再開発の対象となり、閉鎖して工事中になっていました。
沖縄旅行2015-3 ごく普通な観光のことなど ― 2015年07月15日 05:05
夏休みは今日までですので、今日東京に戻る予定です。
旅行中撮り溜めした写真を見ながら、このブログの空気にあうように旅行のことを書くにはどうすれば良さそうか少し考え、「趣味に走った美味しいところ」は後に持っていくことにしました。
そのため、今回は一般的な観光のことを書き、バスの話や道端の話は次回以降に更新します。
これまでは路線バスで沖縄島内を移動することが多かったですが、今回は妻の運転の練習が目的ですので、レンタカーを借りて名護やうるま等の北部を観光。憧れだった「おっぱ牛乳」もゲットしました。
世界遺産にもなった勝連城跡です。13-14世紀に建てられた山城で、琉球王朝の城群として世界遺産に登録された中では最も築城年代が古いものです。
人手だけでよく数百年保つ、これだけ高い城を作ったものだと感心します。土木建築工事の機械化が進んだ今となっては、当時の技はとても想像できません。
何度も沖縄観光をしているのに、北部が手薄(行ったことのある場所の最北がいま大問題になっている名護市辺野古)だったのは、那覇から離れており本数も少なく、路線バスでは往復できても周遊しにくいためでした。
(さらに車両も小振りの「中型車」で、正直に趣味的に今ひとつ萌えなかった)
ジンベエザメが泳ぐ美ら海水族館の大水槽や、
海洋博公園で飼育しているウミガメをじっくり鑑賞しました。
今回の沖縄旅行では、ありがたいことに台風と台風の間に日程が収まり、台風が近いのに安定した天気でした。
山岳部出身なのに海が好きで、いままで沖縄に旅行に行った時は、たいてい体験ダイビングをしていましたが、今回は夫婦でダイビングのライセンスを取り、某電機屋の閉店セールで買い叩いてきた防水デジカメも揃え、準備万端で海に入りました。
すごい綺麗な青色です。あまりの美しさに、言葉が出てきません。
30m防水コンデジの腕試しで、クマノミに隠れるイソギンチャクを一枚。定番?なカットです。
そして、(今回の旅行で見たばっかりとはいえ)水族館でしか見たことないウミガメにはじめて遭遇!
あのウミガメ様と近くで対面し、すごく感動しました。
模型の衝動買いや酒代を節約し、夫婦でライセンスを取ってよかったです。
(つづく)
沖縄旅行2015-4 バス好きの血はやはり大騒ぎ ― 2015年07月16日 07:20
いままでの沖縄行きでは、移動のほとんどをバスやモノレールに頼っていましたが、今回は、レンタカーをずっと借りてました。そんな訳で、今までの旅行と違いほとんどバスを使わない旅程を組となりました(乗ったのは那覇市内の1回だけ)。
しかしいざ現地で現物を見ると、やはりバス好きの血は大騒ぎ。妻から「エンジン音がする度にバスの方振り返ってるね」と言われてしまいました。。。
まずは、今の沖縄のバス事情を象徴する1枚から。
もう20年落ちの米軍スクールバス転用車ですが、フルカラーLEDの行先表示に換装され、いまなお沖縄一の幹線である那覇〜名護線で活躍しています。
15年前に訪れて衝撃を受けた那覇バスターミナルは、2018年の再開発オープンを目指して、工事中で閉鎖されていました。
琉球バス塗装の青とオレンジが逆転した、米軍スクールバス転用車も健在。
1990年代に当時の琉球バスが米軍スクールバス事業から撤退すまで継続して新車が入っていたこと、スクールバスのため路線バスに比べて走行距離が短かったこと、アメリカ人の体格にあわせて大柄の座席を持っていることから、古い車でもいまなお多く残っています。
本州の中古車。車両の仕様から判断すると、関西地区の中古でしょうか。
「ナナサンマル」で入れた車両の入れ替え、沖縄県内バス事業者の経営悪化に伴い、1990年代から多くの中古バスが使われ始めました。沖縄の車両板金修理力は高いものがあり、古い車でもタイヤ周りにサビが見られないのみならず、フルカラーLEDを装備していたりします。
これも本州の中古車。
2000年代に入り、県内のバス会社の経営が最も悪くなった時期は、塗り替えも適当になっています。写真の車は元の車両(都営バス)の塗装を活かして、上半分だけ塗り替えた車両です。
この車両、古いはずですが、メッキのホイールキャップにLED前照灯と手が入っており、来沖の経緯に反して大事に使われていると思われる車両です。
沖縄のバスは、この20年で利用者が半分以上に減ってしまいました。沖縄きっての幹線バスである20(那覇〜名護)系統も、効率的な代わりに輸送力の小さい中型車が導入されています。
そして2010年代、バスに関する規制緩和があり、新規事業者が路線バス事業に入りやすくなりました。
そのため、観光バス事業者も路線バスの営業を始めるようになりました。この車両は在来の路線バス会社が運行していない「やんばる急行バス」。那覇から美ら海水族館のある元部半島への直行バスですが、何でしょうこの車両。本州で高速バスとして酷使された車両に、前面のバンパー・ライト周りは別会社(熊本バス)のツギハギを隠さず取り付けている様に仰天。
なんだか、2010年代のバス業界のカオスを見たような気がします。
そんな思いを込めながら、15年前の面影を追いたくて、「ナナサンマル」営業1号車を撮った同じ場所で、市内線バスの写真を1枚。車両は当然「ナナサンマル」から入れ替わり(入れ替えは中古車で行われたため、もしかしたら2世代入れ替わったかもしれません)、15年前は交番前を曲がって運行していた1番系統ですが、いまではこの系統は1日4便になってしまいました。
そんな沖縄の最新バス事情ですが、バスグラフィックの最新刊に全車両の情報やバスマップも含めて詳細に纏まっています。
沖縄美人のおねいさんかわいい(マテ
(つづく)
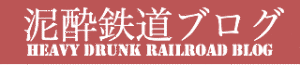






























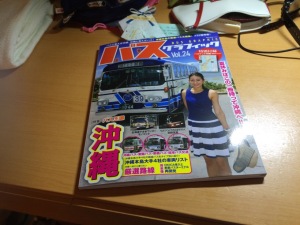


最近のコメント