#2021新春荷電祭り04-クモユ141側面の試行錯誤 ― 2020年12月19日 07:40
1週間経ってしまいました。その間も工作はボチボチ進めております。
流行る気持ちを抑えられず、ランナーから車体を切り出し、ゲートと(古いGMキットの特徴である)車体に表現された「郵〒便」「荷物」のディティールを削ります。
さてさて、クモユ141は側面窓が全てHゴム固定となっており、クモユニ82(3箇所窓が開く)とは若干異なります。これはもう1両分のクモユニ82のキットからHゴム窓切り継ぎで表現します。
今回は、車体強度に影響しない、窓部のみの切り継ぎで工作しようと思います。
試しに1箇所、2連Hゴム窓箇所を車体から切り取り、当該窓を切り抜いたもう片方の車体に嵌め込みます。
接着にはタミヤの緑キャップ(流し込みタイプ)の接着剤を使用し、プラスチックの削り屑を緑キャップ接着剤で溶かしてたパテで隙間も埋めます。
日曜日深夜から朝にかけての工作で、窓が開く3箇所のHゴム窓への切り継ぎを行いました。
月曜日から金曜日の帰宅後、接着剤の乾燥を待ってパテで埋めます。
接着剤が乾いてから車体の平滑削りに移行したのですが、これが難しい・・・
結局窓1箇所は側板ごと切り継ぎに変更しました。切り継ぎ箇所も瞬間接着剤で車体削り屑を埋める工法に変更します。
あと車体側板を平滑に削る際の邪魔になる雨樋も、一旦削って付け直すことにしました。
400番のヤスリでパテを削った後、側板ごと切り継ぎの窓と、窓部のみ切り継ぎの車体とを比較しました。
窓部のみ切り継ぎの車体の方は、やはり車体側板を平滑に仕上げるのが難しく、窓部が凸凹になってしまっています。また、せっかくの窓のHゴムモールドを削ってしまいました。
根本的なところからやり直さないといけないかもしれません。
#2021新春荷電祭り03-着工・動力と車輪について ― 2020年12月13日 00:56
上越線仕様のクモユ141+クモニ83の着工です。
まずは使いそうな部品を広げてニヨニヨするところから。。。
昔のTMSで「工作する素材を眺めて楽しむ」という漫画がありましたが、それと同じでこの状態で眺めるのが一番楽しいです(着工すると楽しみが苦しみに変わる・・・)
まずは動力装置の検討。
愛用してきた旧製品のGM文鎮動力もいよいよストックが無くなってきて、どうしたものか思案した結果、動力はKOKUDEN103系発生品の動力を流用し、クモユ141に仕込むことにしました。
実車の台車はDT21との事ですが、ブレーキシリンダーが台車中央間にしか無いDT33のような形にも見えますので、ちょうどこれで良いようです(確証が持てない・・・)。
合わせて、T車となるクモニ83の車輪をKOKUDEN発生品の黒染車輪に交換します。
写真上が製品付属のシルバー車輪、下が黒染車輪ですが、車輪を交換するだけでも車輪周りが落ち着きます。
#2021新春荷電祭り02-クモニ83の材料の仕入れ ― 2020年11月02日 17:14
早いもので今年も11月です。
今日は先月20日に引き続き休みをいただけましたので、都内に買い出しです。
いつもの秋葉原に加え・・・
今回は新宿の新大久保にも初めて顔を出してきました。
韓流ブームが過ぎた後のアジアンテイスト溢れる大久保通りを抜けると(美味しそうな香辛料の匂いが腹をそそり、昼食を食べてから外出したことを後悔しました)。
路地の中にタヴァサホビーハウスを発見。
ここでパーツを仕入れてきました。
まだ103系電車の工作は続いていますが、そろそろ次作というか、2021年新春の工作ネタを仕入れてきました。
来年春はコロナの影響がまだ残り自宅に篭ることが多い年末年始になりそうですが、テレビを見ているのも退屈なので、模型工作に勤しむことにします。
ちょうどツイッターでは#2021新春荷電祭りという楽しそうなイベントが開かれ、これに便乗して仕掛中(放置中?)のクモユ141を組み立てることにします。
その相棒に、上越線でコンビを組んでいたクモニ83を購入してきました。
ところでクモニ・クモユニの板キットはGMストアに在庫がなく(11/2時点で、秋葉原IMONにクモユニ82とクモニ83の板キットの在庫がありました)、バルクランナーから復元することにしました。
屋根はピタリのものがありませんでしたが、サロ85用で代用できそうです。
#2021新春荷電祭り01-クモユ141のバルクでの検討 ― 2019年06月19日 21:23
秋葉原にお出かけしてきた時、次かその次かまたその次か・・・の工作で作りたいと思っているクモユ141に使いそうなバルクパーツをいくつか見繕ってきました。
クモユ141なのに何故クモハ123?と思われる方もいるかもしれません。
これは少々古いながら、今回作るクモユ141の手本にしたい作例が、メーカーのグリーンマックスから紹介されており、その記事の中でベースにクモハ123を使用しているためです。
他にもこの作例では、ヘッドライトを点灯式にしたりと色々参考になる点が多いです。
さて、模型工作の中で一番楽しい、どんな工作をしようか素材とニラメッコする時間がやってまいりました。
前面の比較。
グリーンマックスのパーツセットに入っていたクモユ141の前面とクモハ123の前面を並べてみます。
ライトや方向幕の成形具合は新しいクモハ123の方が実感的ですが、屋根周りのカーブはクモユ141の方が実感的なような・・・
ここは着工までの悩みどころです。
【2020.11.2加筆】
長らく塩漬けにしてきましたが着工の目処が立ったため、タイトルとタグを修正しました。
クモユ141は旧型国電ではありませんが・・・
荷物電車を安易に仕上げる ― 2017年07月09日 22:19
塗り屋根は500番サーフェーサー(溶きパテ)を買うまで待ちです。
その代わりに、1日で出来る工作。
JNMAで買ってきたクモニ83817(KATOのAssyパーツ)の車体と、大学鉄研の不用品を貰ってきて20年熟成させた金属製クモユニ82(マイクロエース)の整備をします。
両方とも、手持ちの床下(余っているGM・鉄コレ)を嵌めて、お金をかけずにとりあえず走るようにします。
クモニ83の前面方向幕やライトは、製品では光るようになっていますが、KATOの下回りやライトユニットは使わず、余っているエッチングパーツや炙って先を丸くした光ファイバーを使ってお安く仕上げます。
下回りを仕上げてとりあえず完成。スカ色の荷物電車も2両揃いました。
しかし1980年代のマイクロエースの金属製クモユニ82と、KATOのクモニ83の車体高さが全然違います。まるでクモユニ82が低屋根でない感じ。
マイクロエースのクモユニ82は、パンタグラフを含め当時感を大事にしてそのまま遊ぶようにします。
で、クモニ83は湘南色に増結して、上越線の荷物電車や年末の荷物臨電風にして遊ぶことにします。
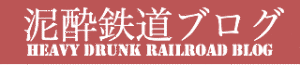






















最近のコメント